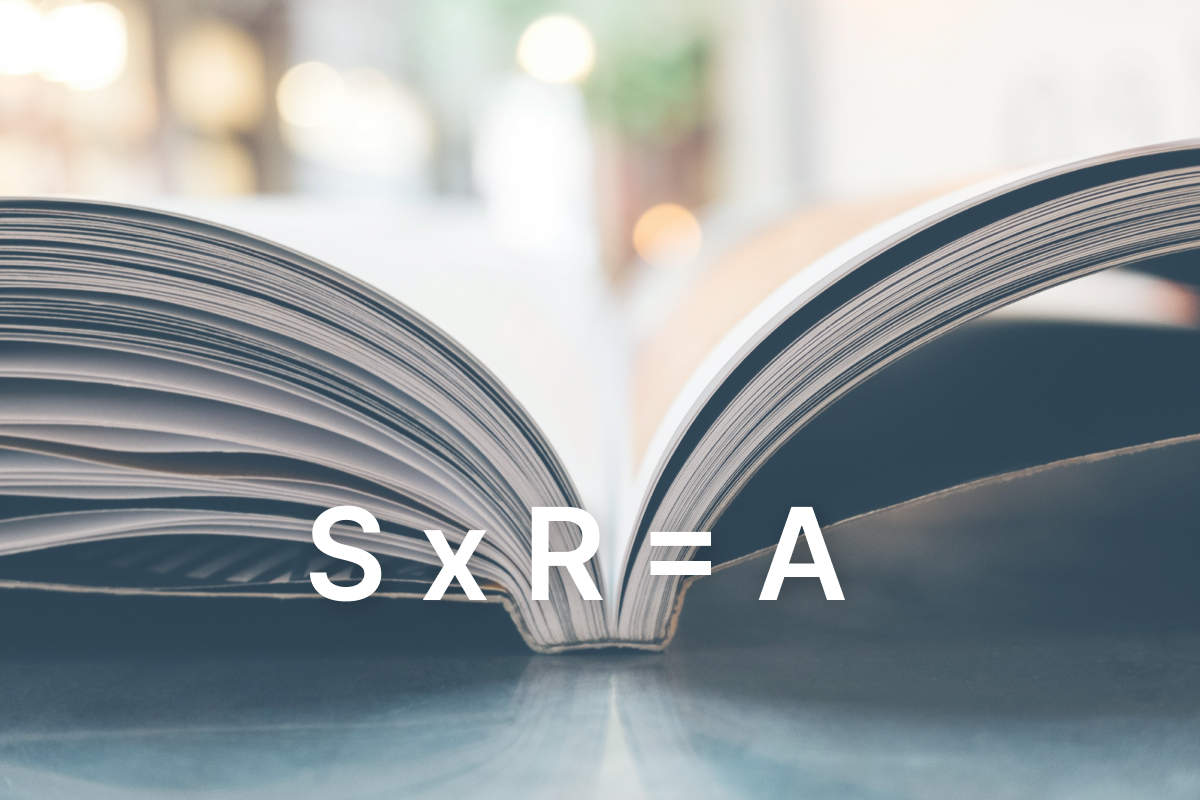羽田康祐著『読書の方程式』は、ビジネス書をただ読むだけで終わらせず、最大限の学びを吸収し、実践に活かすための具体的な方法を教えてくれる本です。実践的なアウトプットの方法や、自分に合ったビジネス書の選び方を教えてくれます。
- ビジネス書は読んでいるけどあまり身になっていないと感じている人
- 1冊のビジネス書から最大限の学びを得る方法を知りたい人
- 自分に合うビジネス書の選び方を知りたい人
私がこの本を読もうと思ったきっかけは、ビジネス書の読み方が知りたくて、Google検索していた時に羽田氏のブログに出会ったことです。ブログ記事の中で紹介されていた『読書の方程式』を読んで、「これは面白そう!」となり、翌日にkindleで購入しました。
『読書の方程式』から学べること
『読書の方程式』から、大きく分けて以下の3つの点を知ることができます。
- なぜビジネス書を読むべきか
- どのようにビジネス書を読むべきか
- 何を読むべきか
1. なぜビジネス書を読むべきか
『読書の方程式』には、ビジネス書を読むことがどのように自己成長、未来の自分への投資につながるかが書かれています。
インターネットに情報が溢れる時代に、なぜわざわざ書籍を買って読むべきなのか。「ネットの情報だけだとやっぱりダメかな」と思っていた私は、この本を読んで「やっぱりそうか。本読もう」と動機づけが得られました。
2. どのようにビジネス書を読むべきか
単に読むだけだと、1週間後には内容を忘れてしまったりしませんか。私は「なるほど〜!」「すごいいいこと書いてある!」と思いながら読んでいても、読み終わった瞬間から忘れ始め、どこが良かったのかも他人にうまく説明できず、もどかしくなることが多いです。これだとせっかく読んでもあまり自分の身にならずもったいないですよね。
本書では「視点読書」や「法則読書」といった著者オリジナルの読書術を使って、読書の効果を最大化する方法を解説しています。本の内容を深く理解し、記憶に定着させ、今の仕事だけでなく将来に役立つストック情報を持つことができるアプローチです。
3. 何を読むべきか
多くのビジネス書が存在する中で、自分にとって最適な本をどうやって選んだらいいか。本書は、課題に応じた本の選び方や、信頼できる著者の見極め方も教えてくれます。書店やAmazonでチェックするポイントもあってとても実践的です。
以降では、なぜ?どのように?何を?の3点について、本からのエッセンスをご紹介していきます。
この記事を読んで、「『読書の方程式』面白そう。自分にも役立ちそう」と思った方は、ぜひご自分でも書籍を手に取って読んでみてください。

著者、羽田康祐氏について
羽田康祐氏は、ご自身のブログで以下のように自己紹介しておられます。
「広告代理店」と「外資系コンサルティングファーム」を行き来したハイブリッドキャリアを持つブランドストラテジスト
ビジネスの第一線で活躍しながら、読書に関する独自のアプローチ、アウトプット法を生み出し、自分自身のキャリアにつなげてきた方です。国内外でのビジネス、コンサルティングの場で、実際にご自身が活かしてきた読書法をこの本で公開してくれています。
1. ビジネス書を読む目的は「視点と法則を増やすこと」
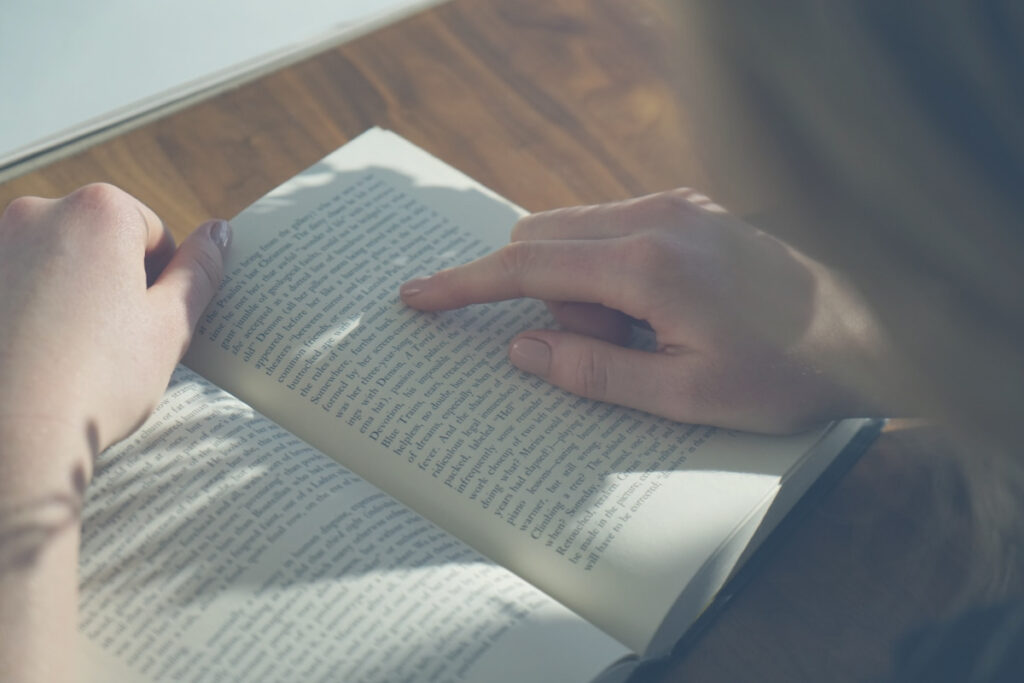
ビジネス書を読む目的は人によりさまざまです。
- ビジネスの教養のため
- 最新の知識や情報を知るため
- ビジネスでの失敗を避け、できるだけ早く成功するため
などなど。
『読書の方程式』では、著者の羽田氏が「少し毛色の違う」と表現しているとおり、少し変わった「ビジネス書を読む目的」が紹介されています。
それが
自分の中に「視点」と「法則」を増やしていくこと
です。
この本では、「視点」と「法則」という言葉が何度もでてきます。そして、書籍のタイトルにもあるように、ある「方程式」がでてきます。
それが、
視点x法則=自分なりの結論
です。
視点と法則が増えると何がいいのか。
自分の中に視点や法則が増えると、ビジネスにおける突破口が見つけ出しやすくなります。
人はある「視点」を通してでしか考えることができない。「視点」が増えれば、それだけ一つの物事をさまざまな角度から見ることができるようになります。「法則」を数多く知っていれば、さまざまな仮説を立てていくことができるようになります。
ビジネス書には、さまざまな業界や立場で活躍してきた第一線の人たちの「視点」や「法則」がたくさん隠されています。ビジネス書著者が積み上げてきた「視点」や「法則」を、この本で紹介されている「視点読書」や「法則読書」をしながら見いだし、自分なりの結論を出してストックしていく。
それが将来、自分のビジネスやキャリアでの突破口となるようなアイデアにつながります。
自分なりの結論を出すことの大切さ
よくある落とし穴が、ビジネス書を読むこと自体が目的になってしまうこと。単なる知識のアップデートで終わってしまうと「頭でっかち」になるだけで実践で活かすことができません。
学びを最大限にし、自分のビジネスやキャリア、生活に活かすには、本書で進めているような読書法とアウトプット法で、「自分なりの結論」を出していくこと。
最初は面倒かもしれないけど、そうすることで「読んで1ヶ月経ったらもう何も覚えていない」みたいな残念な結果を避けることができます。
2. 1冊の本から100%以上の学びを得るための「10倍読書」とアウトプット術

『読書の方程式』では、速読や多読よりも、1冊からの学びを最大化する読書法「10倍読書」を勧めています。
この10倍読書は、本当に共感できた部分でした。ビジネス書を読む目的を「学びを得ること」にフォーカスしていて、1冊1冊を大切に、読み方を変えて何度も読み、読んだものをアウトプットする。こうすれば、「読んだけど内容を誰にも説明できない。1週間後には忘れてしまった」という、私のよくあるパターンから脱却できそうです。
10倍読書の具体的なメソッドとして挙げられているのが以下の読書法です。
- 視点読書
- 法則読書
- 固め読み
「固め読み」については、言葉から大体内容が想像がつくと思います。同じテーマの本を一定期間に何冊も読むことでそのテーマへの理解を深め知識を定着させる方法です。
「視点読書」と「法則読書」は、正直、3回読んでようやく「あ〜こういうことか」とわかってくるくらい、私には「難しい・・・」と感じるアプローチでした。
それだけに、こういう読書法を知って意識するだけで、ビジネス書をサラッと読むだけでは得られない思考力や分析力が鍛えられると感じました。
以下に、視点読書と法則読書の概要をまとめます。具体例とともに学ぶ方がよりよく理解できると思うので、興味を持たれた方は本書で読んでみてください。
インプット・アウトプットが10倍になる読書の方程式視点読書とは
視点とは:どの側面に焦点を当てて物事をとらえているか? という着目しているポイント。
羽田康祐k_bird. インプット・アウトプットが10倍になる読書の方程式 (p.86). フォレスト出版株式会社. Kindle 版.
視点読書は、ビジネス書から「視点」を見つけ、それを抽象化して捉え直すことです。以下の2つのステップで行います。
例)物事に対する「答え」と「答えの出し方」の視点
例)「答え」「答えの出し方」をさらに抽象化します
「答え」の視点→「知識」の視点
「答えの出し方」の視点→「思考プロセス」の視点
法則読書とは
法則とは:「ああなれば→こうなりやすい」という因果関係
羽田康祐k_bird. インプット・アウトプットが10倍になる読書の方程式 (p.135). フォレスト出版株式会社. Kindle 版.
法則読書とは、視点読書を通して見つけた「視点」を起点にして、「ああなればこうなるだろう」と考え、結論をだすことです。以下の2つのステップで行います。
例)「答え」と「答えの出し方」の視点を、法則にする。
「答え」を学んでも → 限定的な、一過性の学びしか得られない
「答えの出し方」を学べば → 応用が効き、一生モノの学びが得られやすい
視点読書で抽象化したものを法則にし、幅広く応用できる「概念」に置き換えられないか、考えてみる。
例)「知識」と「思考プロセス」を、概念に置きかえる。
「知識」は→一過性の「消費」にしかならない
「思考プロセス」は→将来に活かせる「投資」になる
すごい頭の体操になりますね(笑)こういう読み方をする癖がついていれば、ビジネス書のコスパが非常に良くなると思いました。
視点読書、法則読書のほかにも、同じテーマを期間を決めて何冊か読む「固め読み」、記憶をさらに定着させ、将来に使えるヒントをストックするためのアウトプット方法など、大変参考になります。
アウトプット方法については、特に自分が実践しようと思った方法を後述していますので、読み進めていただければと思います。
3. 自分に合ったビジネス書の見つけ方

『読書の方程式』では、自分に合ったビジネス書を書店で見つける方法とAmazonで見つける方法を紹介してくれています。
ビジネス書と一口に言っても、名著から新作、さまざまなジャンルのビジネス書が、その分野の初心者から上級者向けまで、非常にたくさんありますよね。
せっかくXで「面白い!役に立った!」と紹介しているポストを見て興味を持っても、Amazonの評価を見たら「当たり前のことしか書いていない」みたいな批判的なコメントがあったりすること、ありませんか。
値段も1500円くらいはするので、気になるものを何冊も一気に買うのはお財布がつらい。購入しようか、どうしようかと悩んでしまいます。
『読書の方程式』を読むと、自分の持つスキルや目的に合わせて最適なビジネス書を選ぶためのヒントが得られます。
私は国外で生活していることもあり、基本購入するのはAmazonのKindle本です。書店だけでなく、Amazonでの見つけ方、レビューの解釈の仕方についても教えてもらえたのはありがたかったです。
「積ん読」「速読」「多読」などいろいろありますが、個人的には毎月の予算も限られているので、本書で進められている見つけ方を活用して、1冊1冊を大切にしっかり読み込んでいきたいと思いました。
特に心に刺さった点、実践したいアウトプット術
自分が考えられる思考の範囲内が、自分の行動の限界

「ビジネス書を読むと思考力がつく」という章で書かれていた、以下の文章が個人的にかなり心に響きました。
人は、「自分が考えられる思考の範囲内」が、自分の行動の限界になります。 多くのビジネスパーソンにとって理解しておくべき知識は多いですが、他人から与えられた知識のみに頼っていては、他人があなたの限界をつくってしまうことになるのです。
羽田康祐k_bird. インプット・アウトプットが10倍になる読書の方程式 (p.42). フォレスト出版株式会社. Kindle 版.
「ビジネス書を読むと思考力がつく」という見出しではあるものの、ビジネス書を思考停止で読んで、たんに知識をつけるだけでは意味がないということが書かれています。
疑問をぶつけながら、隠れている「視点」や「法則」は何か、と考えながら読むことで、思考力が鍛えられる。思考力が鍛えられると、「正解を探す」人から「正解を作り出す」人になれると。
実践したいアウトプット法:「視点・法則リストを作って将来に役立てる」

自分が読書をする中で発見した、視点や法則のリストを、書籍に書き込んだ状態から、メモアプリなどにストック情報としてまとめていくことが勧められています。
慣れるまで面倒ですが、書籍に書き込んだだけでは「ん〜何かいいアイデアはないかな」と考え込んだ時に、自分が発見していた視点や法則に辿り着くのが難しいので、アプリに転記することが勧められています。
簡単に紹介すると以下のような情報をワンセットにしてメモに追加します。
- アンダーラインを引いた文章
- 発見した視点(or法則)
- 抽象化した視点(or法則)
- 考えられる応用例
大事なのは、情報を1箇所にまとめるということで、その方法は自分のやりやすい方法でOK。
こういう作業が習慣化できると、読書だけでなく、誰かとの会話や、会議、セミナーなどからも「視点」や「法則」を気付けるようになっていくそうです。
ちょっと面倒くさい作業になりますが、コンサルティングや広告業界など、豊富なアイデアや高い提案力が求められる業界で活躍してきた羽田氏がおすすめしている方法なので、実践しない手はありません。
私自身は、ブログに読んだ本のまとめや感想、気に入った文章をまとめていくスタイルをこれからも続けていこうと思っています。(ちなみにブログで発信することもアウトプット法の一つとして紹介されています)
そのブログ記事を作成する際に、「この本からどんな視点や法則が得られたか」ということにも着目して、書いていきたいと思いました。
まとめ
『読書の方程式』は、ビジネス書からの学びを最大化するための読書術、アウトプット術を教えてくれる本です。視点読書や法則読書といった、著者羽田氏のオリジナルの読書術や、視点や法則をストックして自分の将来に生かすアウトプット術など、他の本からは得られないアイデアを教えてくれます。
この記事の中に書ききれなかった部分にもたくさんの学びがありますので、ぜひ気になった方は本書を手に取って読んでみてください。